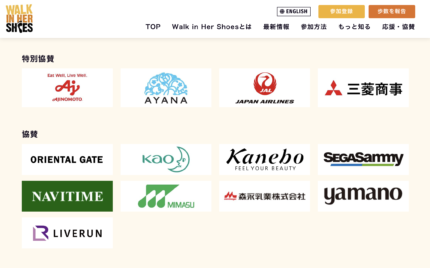赤池 静が「月刊 海外子女教育 2019.10 今月の顔」にて社会起業家としてインタビューされました

ORIENTAL GATE株式会社CEO 赤池 静が「月刊 海外子女教育 2019.10 今月の顔」にて社会起業家としてインタビューされました。
公益財団法人海外子女教育振興財団「月刊海外女子教育」2019年10月号
許可を頂きましたので、文章をそのまま転載します。

【月刊 海外子女教育 2019.10 今月の顔】赤池 静(あかいけ しずか)さん 社会起業家
1972年宮城県生まれ、福岡で育つ。高校入学直後に父の仕事に伴ってアメリカ・コネティカット州に渡るが、4ヶ月後に父の病気治療のため急遽帰国。京都府立洛北高等学校から同志社大学文学部へ進学。卒業後にイギリス・イーストアングリア大学修士課程に進学。帰国後、翻訳関係の仕事を経て25歳の時にネパールへ移住、自然素材の服飾工房を運営する。2014年から活動の本拠を日本に移し、自社ブランド「ネイチャー&クリエーション」を立ち上げる。https://www.natureandcreation.com
たった四ヶ月の「憧れの地」
幼稚園時代からモノづくりが大好き。中学生のころにはすでに自分専用のミシンを持っていて、校則をものともせずに真っ赤な手づくりバッグで通学していた。
「研究者だった父は、自由がいちばん、試験のための勉強はするな、エリート大学なんかつまらない、と言う人。宿題しろと言われたこともありません。だから私、ちょっと自由に育ちすぎちゃったんです」
漠然と生きづらさを感じ、日本には合わない自分はこの先どうしようかと考えていた。
父がアメリカへ行くことになったのは、高校入試の前だった。予定は一年か二年。海外で暮らすことが急に現実のものになった。「そのままアメリカの大学に進学してもいい」とも言われ、赤池さんは期待に胸を膨らませてアメリカの地を踏んだ。
「ここから始めたらいいんだ、と」
しかし、アメリカ生活はわずか数か月で中断する。父の病気が判明して、急遽帰国することになったのだ。
「ようやく慣れてこれからという時期。まだ、憧れのニューヨークにも行っていなかったんですよ」
父の療養のために家族が移り住んだのは京都。地元の公立高校に編入した。
自由でマイペースを許容する校風、私服だったこともあり、赤池さんはのびのびとファッションへの興味を伸ばすことができた。
大学では、教育思想史のゼミに入った。そのなかで取り上げたのが歴史学者朝河貫一の思想。太平洋戦争の開戦阻止に尽力したといわれる朝河は、父の研究テーマでもあった。そのあとを追うように、赤池さんも国際関係の研究に傾倒していった。
在学中から大学院での留学を考えていた。
二十歳のときに「振り袖の代わりに」と母に頼んでアメリカの大学を見て回り、最終的に肌が合いそうだと思ったイギリスに決めた。イーストアングリア大学の修士課程に進学。大学のあるノリッジはアンティークマーケットが有名で、ロンドンにも気軽に行ける距離だった。
同じ十年を過ごすなら
大学院を終えて帰国した赤池さんは、いったん東京で翻訳の仕事に就く。やりがいのある仕事だったが、ストレスも大きかった。
「この仕事を続けて、三十代、四十代が楽しいだろうか」と自問自答し、出した結論は「やっぱりモノづくりがしたい」だった。
このころ、エスニックショップに長く勤めていた母が京都で起業していた。ネパールの女性支援を目的としたフェアトレードの縫製会社。しかし、縫製品は外国人も納得するレベルのクオリティーコントロールが難しく、苦労が絶えないという話を聞いていた。現地にいっしょに行ったこともある。赤池さんは「私がこれを本気でやってみよう」と決心して、ネパールの生産現場に工房を設立した。
「東京でストレスを感じながら十年過ごすなら、その十年をネパールで頑張ってみよう、と思ったんです」
プロとしてものづくりをするために、縫製のパターンも基礎から勉強した。さまざまな問題は起きたが、日本に送り出した製品は着実に売れ、現地ではレストラン併設のショップで在住者や旅行者のファンが増えていった。日本のブランドとのコラボレーションなども進み、区切りとしていた十年が過ぎるころには軌道に乗りはじめていた。
国際関係学を修めた赤池さんにとって、エシカルやフェアトレードはあたりまえだ。物の品質とデザインにこだわっている。目指したものは、安モノでも、奇をてらったエスニックでもない、「自分が着たい服」。人の手で染め、紡ぎ、織り、丁寧に縫製した自然素材の服は、使い込むほどに肌触りがよくなってくる。ゆっくりつくってゆっくり消費してほしい。そういう製品を喜んでくれる人が増えていることを、実感している。
2014年、エスニックとフェアトレードの枠を超えた手紡ぎ手織りのブランド「ネイチャー&クリエーション」を立ち上げた。ギャラリーや百貨店で丁寧に販売している。常設ショップの場所も探しはじめている。新しいブランドも準備中だ。
「気がついたら人生の半分は海外。その最初の一歩はほんの一瞬だったけど、やっぱり行ってよかった。そのあとで飛び出すときのハードルが、ぐんと下がったような気がします」
(取材・文=只木 良枝)