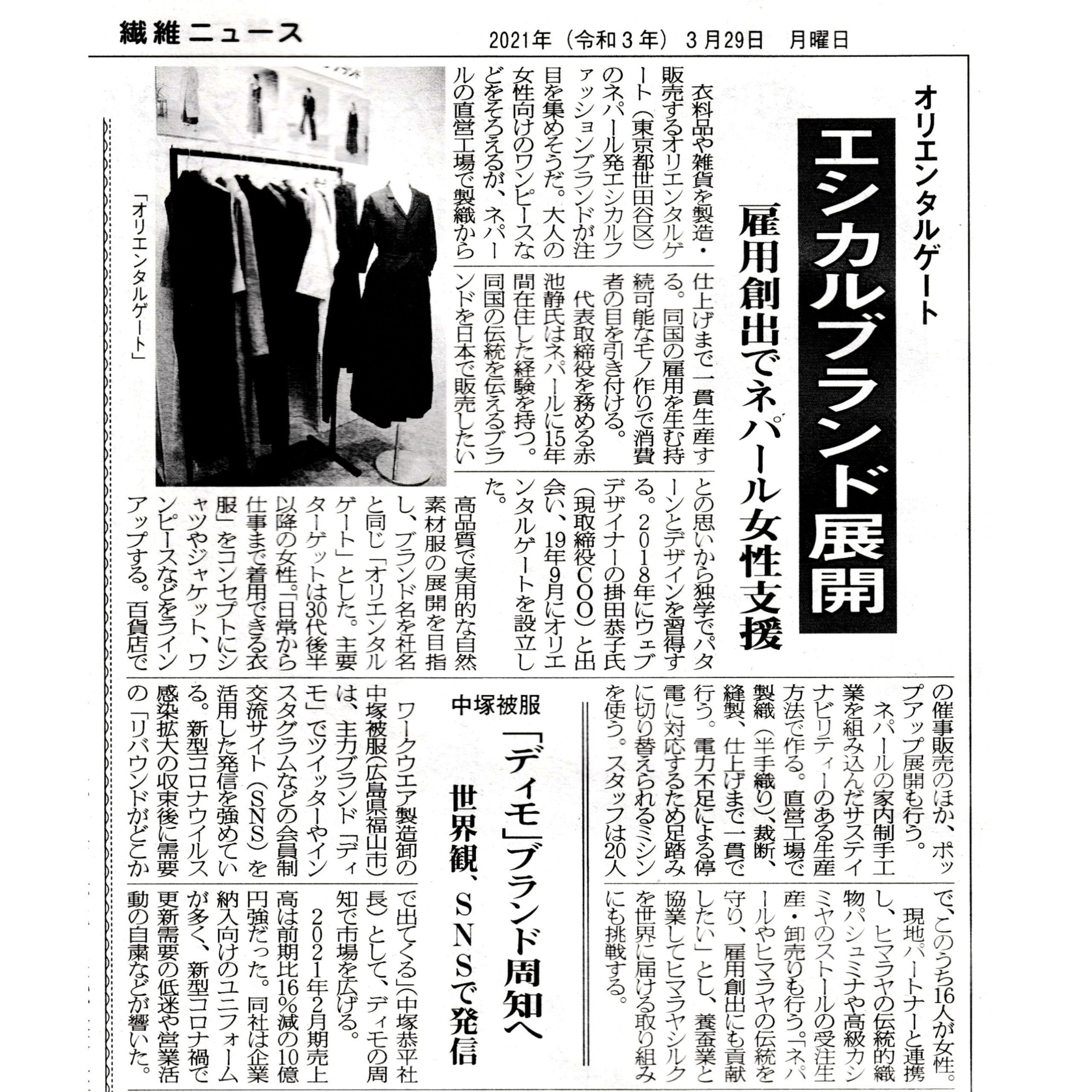パシュミナ ヒマラヤの幻のストールの復興の物語

前の記事の続きです。パシュミナとは、ネパールで数百年の歴史がある、伝統的手織布の名称です。(名前は同じでも、原料と作り方が違うものは別物です。)
このパシュミナの源流は、標高4000m付近のヒマラヤの山岳地帯の村に住む人々と、彼らが飼っている家畜による世界一の秘境における生命の営みだということが、先日放送されたテレビ番組『天空のヒマラヤ部族』という番組で明らかになりました。取材班が入った村まで、地方の空港がある街から一週間もの間、富士山を超える高さの尾根を永遠に進み、険しい峰をいくつも超えて歩き続けていました。つまり、このパシュミナの原毛は、このような道のりを経て、はるばるとカトマンズまで運ばれてきたということです。
そのルートは、パシュミナブームの時に、一度途絶えてしまいました。つまり、中国などから機械紡ぎした糸が入ってきて、飛ぶように売れた時代に、ヒマラヤの山羊の毛は時代から取り残されてしまったのです。何故ならば、山羊のうぶ毛の周りには、その周辺の長い毛も、皮も、汚れも沢山付いているから。また、それを洗って取り除くには、長く手間のかかる工程を必要とするからです。
さらに、その毛を手で紡いでやっと糸になるからです。何故ならば、標高4000mの気温マイナス15度から身を守るうぶ毛は、機械では紡げないほど繊細で細いからです。
しかし、その伝統と技術が失われることはあってはならないと立ち上がった人がいました。ネパールのパートナーのBhes Nath Ghimire さんです。彼は、国費で北欧の大学、大学院に留学した後、長年国連の職員をしていました。プロジェクトで地方を巡り調査する立場だった経験を生かして、何年もかけて、原料をカトマンズまで運ぶルートを復活させたのです。おそらく、点と点をいくつも繋げるような、大変な作業だったと思います。
そして、私はBhesh さんに、共通の知り合いを通じて出会いました。それは2014年のことでした。今こうして、日本でご紹介できることを本当に嬉しく思います。さて、次回はようやくパシュミナの魅力についてです。